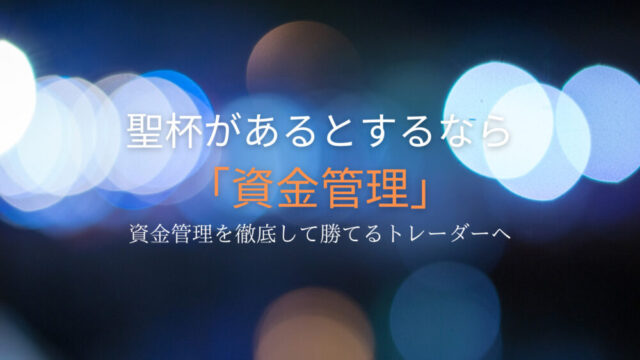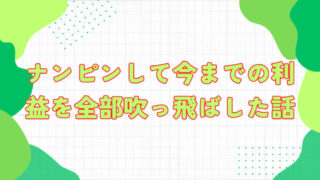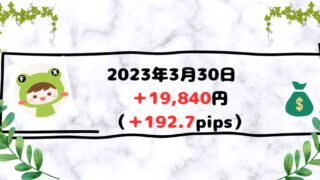- 「トレードをする際に役に立つ心理学を知りたい」
- 「トレードに心理学が重要と聞くけど本当に必要なの?」
- 「心理学を知れたけど、トレードにどういかせばいいの」
このように思ったことはないでしょうか?
私もトレードを始め、心理学について興味を持った時は同じようなことを思っていました。
- 私がおすすめする9つの心理学
- トレードにおいて心理学が必要な理由
- 心理学をどのようにトレードへいかしていくのかを具体的に紹介
トレードをするなら必ず役に立つ心理学を紹介します。
心理学を知っているか知らないかで大きく考え方が変わります。
心理学を知るだけでメンタルの強化に繋がります。
ぜひ最後までご覧ください。

トレードに役立つ9つのおすすめ心理学
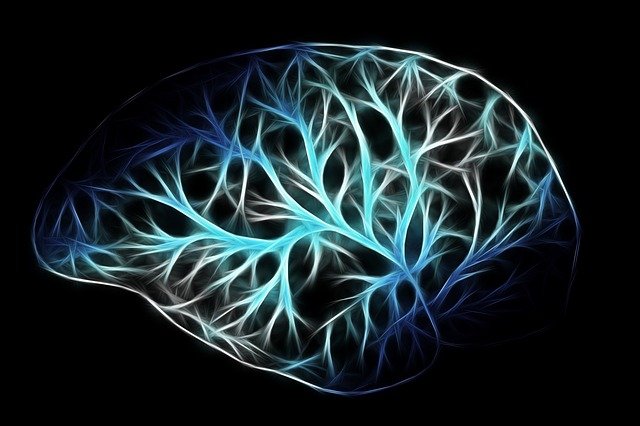
これから紹介する心理学をなるべくわかりやすく解説していきます。
① プロスペクト理論
プロスペクト理論とは「不確実性下における人間の意思決定のモデルの一つ」
えっと…
正直意味わかりませんよね(笑)
簡単に説明すると「人は得をした時より損をした時の方が感情が大きく動く」ということ。
これくらいで思っていただけるといいと思います。
例えば、100万円貰うのと100万円損するのでは、100万円損した方が感情が大きく動くと思います。
このようなかことから人は損失を避けようとする傾向にあるのです。
プロスペクト理論には大きく2つに分かれます。
① リスク回避性
② 損失回避性
この2つに分けられます。
それぞれ説明していきます。
①ー1 リスク回避性
リスク回避性とは、人は「確実に貰えるものは貰いたい」という心理が働くことです。
みなさんは次のA.Bどちらを選びますか?
A 無条件で100万円もらえる
B コインを投げて表なら300万円。裏なら0円
多くの人はAを選ぶ傾向にあります。
期待値で考えた場合Aは100万円、Bは150万円です。
Bの方が期待値は高いのですが、貰えたはずのお金が1円も貰えなくなる可能性ということを避けたくなる心理が働き、確実にもらえるAを選んでしまうのです。
このように人は「確実に貰えるのもは貰いたい」という心理が働きます。
トレードで例えると、「貰えるものは貰いたい」と思うことで早く利益を確定したくなります。
これがチキン利食いの原因の一つなのです。
①ー2 損失回避性
損失回避性とは、人は「確実に損失を出すということから回避しよう」とする心理が働くことです。
次のC.Dどちらを選びますか?
C 無条件で100万円失う
D コインを投げて表なら300万円失う。裏なら0円になる
この場合多くの人はDを選ぶ傾向にあります。
期待値ではCは−100万円、Dは−150万円です。
こちらの場合は損失を回避したくなり、少しでも損失をなくせる可能性のあるDを選んでしまうのです。
このように人は「損失をできるだけ回避したい」という心理が働きます。
トレードで例えると、「損失を回避したくなる」と思えば思うほど損切りができなくなります。
これが損切りができなくなってしまう原因の一つなのです。
② サンクコストバイアス
サンクコストバイアスとは「お金や時間、労働などを費やしたものを取り戻したくなる」心理傾向のことを言います。
*バイアスとは「偏見」「思い込み」「先入観」といったもの
簡単に説明すると「もったいない」と思ってしまい、ずるずると過去のことを引きずってしまうことです。
しっかりと時間をかけて分析したのにも関わらず含み損を抱えてしまったとします。
「あんなにも時間をかけ分析して、資金もそれなりに入れていたのに含み損か…」
「もったいなくて損切りできない」
と思ってしまいたくなります。
このように「もったいない」と思うことによって損切りができなくなる傾向があります。
「もったいない」この感情はトレードにおいて非常に危険なので気をつけましょう。
③ バンドワゴン効果
バンドワゴン効果とは「多数の人が選択している現象が、その選択肢を選択するものをさらに増大させる効果」のことをいいます。
これも正直よくわかりませんよね。
簡単に説明すると「みんなと同じことなら安心」という心理から大多数と同じ行動をとってしまうということです。
トレードで例えると、上昇相場において急上昇が発生して「飛びつき買い」をしてしまい高値掴みとなってその後含み損になってしまうといったところです。
他には仮想通貨において「この仮想通貨はみんなが買っていて人気だし買ってみるか」というように「みんなが買っているから」という理由だけで買ってしまっているようなことをいいます。
「みんなが知っている情報」=「大衆が知っている情報」
大衆心理で見た時、「みんなが知っている情報」はあまり「優位性」がないことが多いので損をする可能性が高いです。
「みんなと同じだから安心」この心理に陥っている状態での行動には気をつけましょう。
④ ギャンブラーの後謬(ごびょう)
ギャンブラーの誤謬(ごびょう)とは「ある事象の発生頻度が特定の期間中に高くなった場合に、その後の試行におけるその事象の発生確率が低くなると信じてしまう心理状態のこと」
わかりにくいので具体例をあげて説明します。
コインを投げて連続で表が5回出たとします。
この時、次コインを投げたら「そろそろ裏が出るだろう」と思ってしまうことです。
確率で考えると、表、裏それぞれの出る確率は1/2と同じはずなのに偏った考えになってしまいます。
トレードでいうと、これだけ上がり続けていたら「そろそろ下がり始めるだろう」と思って感覚だけで逆張りしてしまうことです。
「値頃感」でのトレードをしてしまう原因の一つがこの『ギャンブラーの誤謬(ごびょう)』に気付かぬうちに陥っているからです。
⑤ 認知的不協和
認知的不協和とは「自分の正しいと思う考えや行動とは違うことをした時の不安感をなくす為に、その時の状況に合わせて考え方、行動を変え自分を正当化する」ことです。
トレードで例えると、マイルールで決めているはずの、エントリーから決済までの計画が根拠もなく自分の都合に合わせて変更してしまうことがあげられます。
エントリーに関しては自分のエントリーポイントまで待てずにたくさんエントリーしてしまい「ポジポジ病」になる。
含み益が出た時には利確位置まで待てずに「チキン利食い」となり、
含み損を抱えると、何か理由をつけて損切りができなくなり「塩漬け」となってしまいます。
認知的不協和に陥ることによって一度決めたこと(マイルールを破る)を変えて自分を「正当化」してしまうことによって大きな損失を出してしまうことにつながるので気をつけましょう。
⑥ レイク・ウォビゴン効果
レイク・ウォビゴン効果とは「自分の能力は他の人と比べて優れていると、自分を過大評価してしまう心理傾向のこと」です。
レイク・ウォビゴン効果は初心者や勝ち始めてた人が陥りがちな印象です。
始めたばかりの人が「自分は負けるはずがない」と何故かよくわからない自信に満ち溢れてトレードを始めます。
そして大きな損失をだしてしまう。
実際に私もそうでした。
勝ち始めたかといって「もう負けないだろう」と大勝負に出て大損する。
これも「自分は他の人より優れている」という心理傾向からなる行動です。
トレードを始めたばかりの人、勝ち始めた人ほど「レイク・ウォビゴン効果」に陥らないように謙虚にトレードするように心がけましょう。
⑦ 自己奉仕バイアス
自己奉仕バイアスとは「成功した時は自分の能力、失敗した時は誰か(物)の責任としてしまう」ことです。
人は無意識のうちに自尊心を保つために自分の行動を正当化してしまいます。
そのため自分の失敗を認めたくないという感情が出てくるのです。
失敗を認めたくないということから「失敗した時は誰か(物)のせい」にしてしまいます。
トレードにおいては、損切りをした、含み損を抱えた時に、「相場の動きが悪い(相場が悪い)」「指標の結果が悪い(指標のせい)」など失敗の原因を「自分以外の何かのせい」にしてしまうことがあげられます。
逆にトレードが上手くいくと「自分の能力のおかげ」と思い込んでしまい反省を忘れてしまいます。
自己奉仕バイアスに陥ってしまうとトレードが向上しにくいです。
しっかり失敗したら自分の責任と思って反省して改善をするようにしましょう。
⑧ どうにでもなれ効果
どうにでもなれ効果とは「一度失敗をした時に自制心が崩れる」ことです。
具体例をあげると、ダイエットしていてお菓子を食べないと決めていたのにも関わらず食べてしまい、お菓子を食べた罪悪感から自分を救うためにまたお菓子を食べてしまい、結局ダイエットが続かなくなってしまうようなことです。
トレードでは、損切りのマイルールを破ってしまいその罪悪感から損切りができなくなりそのまま塩漬けにして大損となってしまうことがあげられます。
マイルールを破りマイルールとは真逆のことをしてしまうことがこの「どうにでもなれ効果」によるものなのです。
もしマイルールを破ってしまった時こそ冷静になりこの「どうにでもなれ効果」を思い出してすぐに立て直すようにしましょう。
⑨プライミング効果
プライミング効果とは「先に得た情報が、今後の行動(思考)に影響してくる」ことです。
わかりやすい例だと、「10回クイズ」がわかりやすい例だと思います。
みなさんも1度はしたことがあると思います。
「〜を10回言って。」「それじゃあ〜は何?」ってやつです。
かなりの確率で答えを間違えますよね。
10回クイズのように「先に得た情報が優先的に処理されてしまう」ことを認識しておきましょう。
トレードではファンダメンタルズ分析、テクニカル分析において証券アナリストや有名人の発言によって自分のトレードに影響してしまうことあります。
他の人の情報を信じ込まず、しっかりと自分で情報を仕入れて、自分で判断し、腹落ちさせてから行動に移すようにしましょう。
「プライミング効果」に惑わされず、誰かがなんと言おうと最終的に決めるのは自分でするようにしましょう。
なぜトレードで心理学(メンタル)が重要なのか

よくトレードは心理学(メンタル)が重要と聞きますよね。
結論として
「心理学を知ることによってメンタルが鍛えられてより良いトレードができる」
ようになります。
トレードに心理学(メンタル)が必要な理由
①チャートは大衆心理で動いている
チャートの値動きは大衆心理で動いていると言われています。
そもそも大衆心理とは「人は集団の中で生活しており、自分の考え、判断より周りの意見や行動に合わせてしまうこと」です。
特にFXでは9割の人が負けると言われています。
毎回大衆心理通り動いているのであれば9割も負ける人は出てきませんよね。
大衆心理通り動くこともありますが、大衆心理とは逆の動きをすることが多いです。
チャートには伝統的なチャートパターンが存在します。
「このチャートパターンが出たら次はこう動く」
トレード本にはこのようなことがたくさん書いてあります。
しかし実際トレードをしていてチャートパターン通り素直に動いたことって少ないのではないでしょうか。
こうして大衆が考えるであろう動きと逆の動きをとることによって、その少数派の人が勝っているという仕組みです。
大衆心理とは逆の動きをすることで「優位性」が生まれて利益を上げられやすくなるのです。
初めに紹介した9つの心理学を知りさらに大衆心理を知る。
これはトレードをするにあたりかなり重要になります。
②正しい思考が、正しいトレーディングである
「正しい思考が、正しいトレーディングである」

トレーダーの中ではかなり有名な著書「デイトレード」の一文から抜粋した言葉です。
「デイトレード」は手法ではなくトレードにおける心構えといった心理、メンタルに関することが書かれた書籍となっています。
「デイトレード」では何度も思考(メンタル)が重要だと書かれていることから、トレードにおいてメンタルは必要なんだとわかります。
【送料無料】デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術/オリバー・ベレス/グレッグ・カプラ/藤野隆太
例えば、長期的に見れば勝てる手法があったとします。
ではこの勝てる手法を使い続けて、もし不運にも数回負けが続いたとします。
使い続けたら勝てると分かっていても負けが続くとどうしてもやり方を変えたくなりませんか?
このように頭の中では分かっていてることでも不運なことが連続で起きると変えたくなってしまいます。
素晴らしい手法があっても使い続けることができなければ意味がありません。
そのためにやり方を変えたくなる気持ちを抑え込むためには「正しい思考」を身につける必要があります。
結果としてトレードをする際には「正しい思考」(メンタル)が必要だということがわかります。
心理学をトレードでいかす方法

今回紹介した心理学をトレードで具体的にどのようにいかすのか説明してきます。
結論として、今回紹介した心理学をもとにマイルールを設定することです。
マイルール通りにトレードするということは大切だとよく聞くと思います。
なぜマイルールが必要かというと、マイルール通りトレードできなければ感情的なトレードが増えてトレードの良し悪しの判断がつきづらくなります。
そのためトレード毎の問題がわかりにくくトレードが向上しづらくなるからです。
感情的なトレードをなくすために今回紹介した心理学の罠に陥らないようにする具体的な方法を紹介します。
- ①プロスペクト理論、②サンクコストバイアスに陥らないようにするには「エントリー時には利確位置と損切り位置を決める」ことによって解決できます。この時に注意しなければならないことが1つだけあります。
「損切り位置を損失方向に動かさない」
これだけは守るようにしなければマイルールを作る意味がありません。 - ③バンドワゴン効果、④ギャンブラーの誤謬(ごびょう)、⑨プライミング効果では「その日のシナリオを考え、明確にエントリーポイントまで決め、シナリオ通りの動きをした時だけトレードする」ようにすると解決します。このようなルールを決めることによって無駄なトレードが減り「ポジポジ病」の改善にもつながります。
- ⑤認知的不協和、⑧どうにでもなれ効果では「マイルールを破ってしまった時には、損益に関わらず決済する」ことで解決できます。マイルールを破ってしまったということはエントリーの根拠、決済の根拠が崩れてしまっています。
そんな時は一度思い切って決済し、一度冷静になる必要があります。
冷静になってからしっかりと反省して問題点を洗い出し次に繋げるようにしましょう。 - ⑥レイク・ウォビゴン効果、⑦自己奉仕バイアスでは「トレードで失敗し、損失を出してしまった時は必ず自分責任の問題点を1つ以上出すようにする」ことで解決できます。勝ちトレードの時でも何か問題点を探せるとなおよいと思います。
謙虚な気持ちを忘れないようにしましょう。
このようなマイルールを設定することにより、感情によるトレードを減らせるようになります。
感情によるトレードを減らすことで必ずトレードは向上します。
一度騙されたと思って上記の4つのマイルールのどれかを試してみてください。
きっと感情によるトレードが少しは無くなるはずです。
まとめ

今回紹介した9つの心理学を簡単にまとめてみました。
- プロスペクト理論…「チキン利食い」「損切りができない(塩漬けにしてしまう)」
- サンクコストバイアス…「もったいないと思うことにより損切りができない」
- バンドワゴン効果…「飛びつき買い」「みんなと同じだから安心」
- ギャンブラーの誤謬(ごびょう)…「値頃感でのトレード」
- 認知的不協和…「間違いを認めず自分を正当化する」
- レイク・ウォビゴン効果…「自分を過大評価する」「謙虚さがない」
- 自己奉仕バイアス…「失敗した際他責ではなく自責で考える」
- どうにでもなれ効果…「ルールを破ったことからなげやりになる」
- プライミング効果…「他人の発言に影響を受ける」
今回紹介したこの9つの心理学を知っているだけで自分のトレードを客観的に見れるようになりトレードが向上します。
上手くいかない時こそ一歩引いたところから自分のトレードを見てみると、今回紹介した9つのどれかの心理学に陥っていることが多いです。
いきなり全部の心理学を意識することは難しいと思うので初めの覚えやすいものからゆっくりでいいので覚えてください。
必ずトレードが向上します。
トレードでは心理学(メンタル)が必要となってきます。
まずは大衆心理について考える癖をつけるようにしましょう。
相場格言に「人の行く裏に道あり、花の山」という言葉があるように
大衆とは逆の行動をとることにより「優位性」が出でます。
大衆心理を考えてトレードをするように心がけましょう
次に9つの心理学を知り実行することで「正しい思考」が身につきます。
「正しい思考」を身につけると自然と利益も出せるようになるはずです。
そしてマイルールを設定して感情的なトレードを無くしていきましょう。
マイルールを設定する際には必ず自分のトレードスタイルにあったルールを設定してください。
今回紹介したマイルールを参考にするのもいいですが、必ず自分でアレンジしてください。
相場の世界では誰かに頼っているだけではいつか退場することになります。
自分で考えて行動することが何より大切なことです。
最後にトレードはメンタルの基礎がしっかりとしていなければ必ずどこかで崩れます。
常にメンタルを鍛えるように心がけましょう。